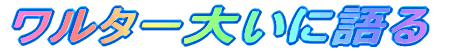
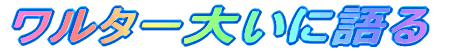
このコーナーは、ワルターが様々な媒体(著作、リハーサル・インタビュー記録等)で語った
なかで、印象的なフレーズだと思ったものをまとめたものです。
みなさんもお気に入りのがあったら教えてくださいね!
ナポレオンは死んだ ― だが、ベートーヴェンは生きている。自伝「主題と変奏」より
音楽というものは、常に交代するその感情の表現にかかわりなく、慰めという永続的な使命を持っている。不協和音は協和音に向かおうと努める。そして解決されずにはいない。どんな音楽作品も協和音で終わるのである。だからエレメントとしての音楽は楽天的な性質のものであって、私は、自分の生まれ持った楽天性はこれと関係があるのだと信じている。
自伝「主題と変奏」より
![]()
感謝して私は生き、過去を眺め、未来を望み − そして私は上方を仰ぐ。
70歳の誕生日が近づいてきみは絶望感しきりとのこと、それはぜひよしてもらいたいものです。ぼくの場合それがすんでもう11年になりますし、請け合っておきますが、自分に苦痛を与えることではなかったのです。それに、いつかきみが成長しきって終わるとは信じられず、かくして、この偉大な体験事は、本来ならきみの自信を強めるはずです。
1957.8.5 ロッテ・レーマンへの手紙
生涯を通じて私には歌があった
![]()
モーツァルトは一小節ずつ表情を変えなければならない。
![]()
あなた方はまだ歌おうとしている。もっと死の恐怖を叫んでください。
![]()
大いなる愛の力と愛の充溢とから、音楽は湧き出るのです。信仰篤き人々、愛し合う人々、嘆き悲しむ人々、祈る人々に対して、音楽は恵みの雨となって惜しげもなくその上に降り注ぎます。
彼女はわれわれの生活に明るさと喜びをもたらしましたが、今は暗くて悲しいものになりました。そして喪失の上に加わるのが、自分がもっと烱眼で注意深く力強かったらと思う苦痛です! このように陰鬱で苦悩に満ちた状態で、どうやって音楽をすればよいか分かりません。あなたがたから私の使命を思い出すように励ましのお言葉をいただきました。使命を忘れず義務を尽くすつもりですが、私はもう若くはなく、必ずしも健康ではなく、グレーテルにたいする私の関係の謂いであった、力の源泉が自分には欠けております。
私が嘆きますのをお許しください―心からの友情のお悔やみについほろりとして、こんな告白をした始末です。私のグレーテルに勇気で負けないように、自ら努めてみるつもりです。われわれの心からなるご挨拶、われわれの尊敬と友情と愛情とをお受け取りください―
ワルターの次女グレーテ・ワルターは、ドイツの映画製作者ローベルト・ネパハとの不幸な結婚を解消したく思い、すでに彼とは別居して、両親のもとで暮らしていた。彼女が同意してなされた「最後の話し合い」の最中に、彼は彼女を射殺して自殺した。彼女が他の男(エツィオ・ピンツァとされる)に向かうかと思うと耐えがたかったからである。この月18日、チューリヒでのことだった。時はルツェルン音楽祭のシーズン中で、凶報に接して茫然自失するワルターに代わり、トスカニーニが指揮棒を握った。
老成の仕事はどんどん進んでおります。今ちょうど、グスタフ・マーラー最大の傑作、「第九交響曲」のレコード完成を目前にしていますが、あるいはご存知かもしれぬとおり、「大地の歌」とともに彼の死語初めて発表されたもので、その初演をぼくが指揮したのです。それは1912年までさかのぼること、マーラーの「第九をヨーロッパで最後に演奏したのは、ヒトラーのウィーン進入直前でした。レコード録音は当時の演奏会その場でなされて、破局を迎える間に幸いにもぼくが契約していたオランダへ転送されました。当時はロッテのことでたいへん心配していて、必要な注意を視聴レコードに向けられず、それゆえ、これはすこぶる不満足な結果になったのです。この不運な事件はもとよりぼくの心にのしかかっていたのですが、それにたいして今度は完全に成功したものを差し出せます。目下の録音はかような完全成功を期待させますし、遠からぬうちにみなさんも納得されることでしょう。
1961.2.3 カチャ・マンへの手紙
私のまじめな努力のほどは、ある私の「発明」に如実にあらわれていると思う。そのおかげで、たとえばメンデルスゾーンの変ホ長調の「無言歌」にあるような、ふつうの八分音符と三連八分音符とを同時に弾く組み合わせを、正確なリズムで把握することができるようになった。つまり、街路を急ぎ足で歩きながら、二歩進むあいだに規則正しく「一、二、三」と大声で数え、「一」が常に左足とかさなるようにする。次には三歩進みあいだに正しく「一、二」と数え、「一」が左足と右足に交互にかさなるようにしたのである。ふつうの音価をもつ音符に、正確な三連音符をつけることは、こうしてまもなく造作ない習慣になった。
自伝「主題と変奏」より
![]()
家庭の経済状態はさほど悪くはなかったように思われようが、実際は極度にきりつめた生活であった。私は当時もその後も、ぎりぎりの窮乏に苦しむことこそまぬかれたけれども、あの限られた我が家の生活状態のことはいまでもよく覚えている。
しかし、このつましいユダヤ人の家庭には、平和と善意と品位とが支配していた。私は両親のあいだの「どたばた」や、家庭生活における粗野な、それどころか不潔な言葉さえ、ひとつとして思いおこすことができない。
自伝「主題と変奏」より
![]()
呼び戻された私は賞賛の言葉と、熱心に努力しなさいという忠告とを受けた。最後にラーデケは、ほんとうに私をわくわくさせるような証明書を書いてくれた。それは、「彼は全身これ音楽なり」という言葉で結ばれていたのである。根源的な音楽性の有無をとりわけ印象的な形で確認しようとしたこの美しい言葉を思いおこすと、私はいまだに喜びでいっぱいになる。
自伝「主題と変奏」より
![]()
私の「第一交響曲」の初演は、1908年に私自身の指揮によってウィーンでおこなわれた。私はこの曲をその後にも、たしか1909年に、プフィッツナーに指導されていた演奏会のひとつで指揮した。「第二交響曲」と「『シラーの「勝利の宴げ」による合唱と管弦楽のためのバラード』は、もはや演奏を試みることはしなかった。これらの作品によって、自分の創造的な天分に対する疑いが確かなものになったからであった。ただアルノルト・ロゼーに捧げた「ピアノとヴァイオリンのためのソナタ」だけは―たぶん私にとって今日なお価値のある中間楽章のせいであろうが―当時の自分自身に対する拒否をもうしばらくのあいだ猶予してくれた。
自伝「主題と変奏」より
![]()
シェーンベルクの勇敢さと惑いのない態度に、私はどれほど驚嘆し、その選ばれた音楽的存在に、どれほど深く浸透されたことであろう。また後期の室内楽や声楽曲にしても、そのかなりの部分が私の心を引きつけた。それにもかかわらず、邪道であると思われる彼の道に、私はますますついて行けなくなった。そして、威風堂々とした彼の存在に対する精神的な共感は、私には抽象的で実験的であると思われるこれらの音語の音楽的な拒否と、今日にいたるまで和解に達してはいないのである。彼の「グレの歌」の英雄的なロマン性、崇高な叙情性、怪奇な大胆さに私は深い愛着を感じ、この強力な作品を幾度も指揮したものだし、また「浄夜」も弦楽合奏用の譜面によって、やっと1943年に再演できるという喜びを味わった― だが、四重奏曲以後の作品は、私の音楽的体質からいって手にあまるのである。アルノルト・シェーンベルクが妥協することのない純粋な理想主義者であるばかりでなく、強力な独自の直観を具えた音楽家でもあることは、疑いをいれない。私は真剣にそう思っているので、もしも来世で音楽的知覚のもっと高度な器官によって教化され、自分の初歩的で地上的な無理解に対して彼に赦しを乞うことができたら、さぞ仕合わせなことであろう、と断言してはばからない。
自伝「主題と変奏」より
![]()
ところで、鼻かぜをひいても生きて働くことはできる。いやそれどころか、古い民間伝承によれば、鼻かぜをひいていると他の重い病気にはかからないのだそうである。
しかしいずれにせよ、鼻かぜよりももっと有効な予防法を与えてくれたのは、私が運命に深く感謝しているひとつの天分、つまりHumour(諧謔)であった。
自伝「主題と変奏」より
![]()